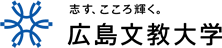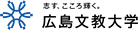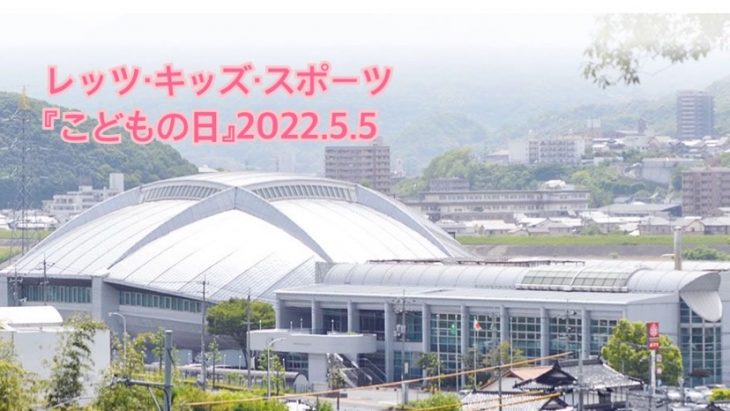- 2024.7.4
- 教育学科
模擬保育に取り組んでいます
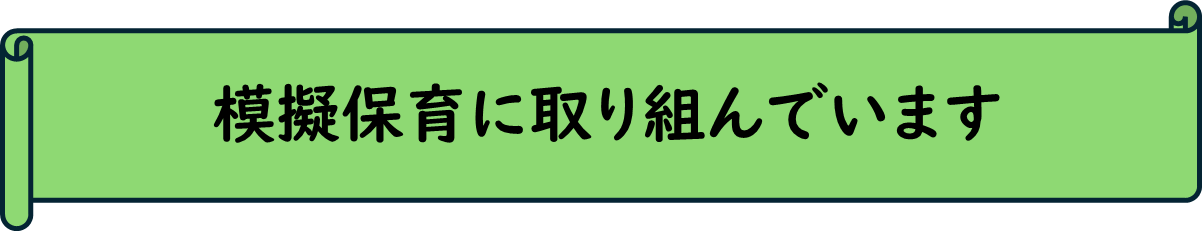
幼児教育コース3年生は、教育実習Ⅰの授業で模擬保育に取り組んでいます。“模擬保育”??… 聞きなれない言葉ですよね。遊びの計画を立て、学生が子ども役と保育者役になって学ぶ形式です。その様子をご紹介する前に、模擬保育室をご案内しましょう。
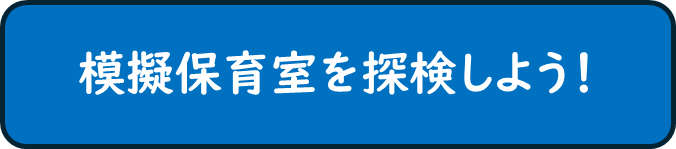

1号館1階にある模擬保育室は、幼稚園や保育所の保育室を再現しています。
保育室の前面は、子どもが活動に集中しやすい環境づくりのために、掲示物を貼らないようにしています。
実際と同じ机と椅子、電子ピアノを置き、子どもと目線を合わせるための保育者の体勢、電子ピアノでの弾き歌いなどを、体験的に学び、実践できるようにしていきます。
お道具箱も設置しています。お道具箱のなかには、クレパスとハサミやのりが入っています。のりやクレパスを確認して補充もします。のりを使う際の手拭きも準備しています。


保育室内には教材棚もあり子どもの活動に応じて教材が提供できるようになっています。

掃除用具入れには、ホウキやちり取りもありますよ。家庭では、あまり見ない掃除用具ですが保育現場では使われています。

乳児保育室を想定して、外の景色や吹く風に触れながら安全に過ごすための柵も再現しています。
鍵を設置して安全面の配慮がされています。
保育室の配慮や工夫はご存知でしたか?発見はありましたか?
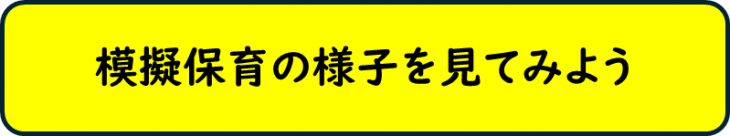
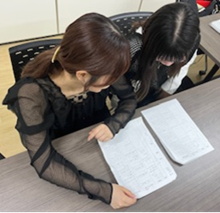
続いて、模擬保育室で、実施している模擬保育について紹介します。担当教員に指導を受け、学生同士で教材を研究したり、遊びの展開を考えたり協議しながら遊びの計画(指導案)を立てます。
保育者役は、模擬保育当日までに実際に模擬保育をしてみます。通称“モギモギ”と言われ空コマを活用して取り組んでいる姿が、学内のあちらこちらで見られます。
模擬保育当日は、実習を想定した服装で出席します。保育者役は環境を整備し、教材を配置します。子ども役は、子どもの発達を踏まえて動きを考え、幼児になり切れるように事前学修します。
模擬保育終了後は、指導計画案の内容や保育実践について振りかえり協議をします。保育者役は保育の構想に続いて、成果と改善点を発表し、幼児役立場から確認したい点や良かった点と改善案などが出されます。

指導計画案の内容から保育者の意図したことを実践に移す方法まで協議します。回数を重ねるごとに活発な意見交流となっています。 学生からは、指導計画案を作成しただけでは気づけないことがあり、模擬保育をして学ぶことが多いとの声が聞かれます。


 幼児教育コースでは、模擬保育室を活用して授業の事前事後学修に取り組んでいます。模擬保育はもちろんのこと、8-9月に実施される保育所実習に向けて、オムツ替え等の練習もしています。昨年度、学生から赤ちゃん人形を使ってオムツ替えや授乳の事後学修をしたいとの要望があり、空コマを活用して取り組めるようにしています。
幼児教育コースでは、模擬保育室を活用して授業の事前事後学修に取り組んでいます。模擬保育はもちろんのこと、8-9月に実施される保育所実習に向けて、オムツ替え等の練習もしています。昨年度、学生から赤ちゃん人形を使ってオムツ替えや授乳の事後学修をしたいとの要望があり、空コマを活用して取り組めるようにしています。